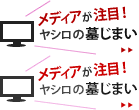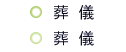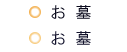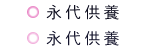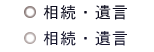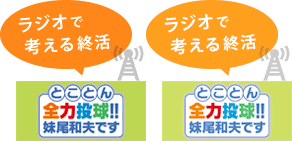終活サポート > ラジオで終活日誌
ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
第97回(2015/12/29放送)
- 妹尾:
- 今日も、これからの人生を楽しく、前向きに送るための「終活」について
僕たちのミニコントも交えながら語り合っていきます。
- 安井:
-
今日のテーマは『葬儀と葬儀社の起源について』です。
それでは終活劇場、はじまりはじまり……
- 男(妹尾):
- あのー、すいません。お電話した妹尾ですけど……
- 社員(安井):
- ああ、妹尾さまですか。私、とことん葬儀社の安井と申します。
本日は、葬儀のご相談ということでしたよね?
- 男(妹尾):
-
ええ、いま流行の終活っていうんですか?
僕はまだ早いって言ったんですけど、家内が今のうちから
自分の葬儀のことは自分で決めておけって言うもんですから。
- 社員(安井):
- とても良いことだと思いますよ。
- 男(妹尾):
-
でもね、自慢じゃないけど、僕はこの世の中のあらゆることを
知り尽くした男でね。別に葬儀のことなんて、いざという時に
パパーッと適当に決めようと思えばできるんですよ。
- 社員(安井):
- へえー、世の中のことを何でもご存じなんですか……
では、葬儀のこともお詳しいんでしょうね?
- 男(妹尾):
- もちろんです。僕にわからないことはありません!!
- 社員(安井):
- じゃあ、話が早いですね。とりあえず、お通夜はどうなさいます?
- 男(妹尾):
- え? お、お、お、おやつ??
- 社員(安井):
- いやいや、おやつじゃなくて、お通夜。
- 男(妹尾):
- ああ、そっちね。そんなもんは適当に2、3人前注文しておけば―
- 社員(安井):
-
はぁ? 2、3人前注文?何を言ってらしゃるんですか?
あ、ひょっとして、お通夜のことご存じないんじゃ?
- 男(妹尾):
- そんなわけないでしょう。僕は何でも知ってるんですから。
ハッハッハ、さっきのは冗談ですよ、ハッハッハ!
- 社員(安井):
- では、告別式はいかがなさいますか?
- 男(妹尾):
-
こ、こ、こ、こくべ、こくべつしき?
えっと、まあ、そんなもんは…そうだ、ミディアムで結構です。
- 社員(安井):
- はぁ?ミディアム? 焼き加減のことをおっしゃてるんですか?
- 男(妹尾):
-
ああ、間違えた間違えた。ちょっとした勘違いだよ、ハハハ……
告別式だろ?告別式は、ほら、大盛りで!あと、生卵も付けようかな。
- 社員(安井):
- 告別式の大盛りで生卵付き?あの、何をおっしゃているのか……
- 男(妹尾):
- じゃあ、ハーフ&ハーフでいいや。うん、それそれ!
- 社員(安井):
- まったく……なんにもわかってないじゃない。
- 妹尾:
-
さて、誰かが亡くなったら「お通夜」や「葬儀」「告別式」をしますが、
こういった儀式は、いつ頃から、何のために行われるようになったのか、
ご存じでしょうか?
「お通夜」は、奈良時代には、すでに行われたいたことが確認されているそうです。
では、何のために「お通夜」という儀式があるかというと、一説によると、
もともとは、みんなで一晩中、故人の思い出や良いところなどを語り合って、
故人がもう一度よみがえることを願った儀式だとされています。
でも最近では、夜6時頃から一時間ほどの「半通夜(はんつや)」が一般的ですね。
- 安井:
- もとの意味合いも薄れていますし、お通夜は形式化しているんですね。
- 妹尾:
-
ただ、「葬儀」の起源は定かではありません。
もともと日本では仏式の葬儀はあまり行われず、神主さんが神道の葬儀を
行うことがほとんどだったようです。
それが江戸時代くらいに仏教と神道が混ざった今のような葬儀の形が
できあがったという説もあるようです。
「告別式」が初めて行われたのも古いことではなく、明治時代だと言われています。
- 安井:
- 今のような葬儀と告別式の形は、そんなに古くない儀式なんですね。
- 妹尾:
-
ちなみに、「葬儀」と「告別式」の本来の意味合いを知っていますか?
「葬儀」とは、遺族と近親者が故人を成仏させるために行う儀式です。
そして、葬儀に参列できなかった知人や友人が、故人に最後の別れを告げたのが
「告別式」です。
「告別式」は最後の別れの場ということで、昔は葬儀の後、遺骨を墓地に埋葬する
直前に行う儀式だったようです。
それが今では葬儀と一緒に「葬式」として行われることが多くなっていますね。
- 安井:
- 葬儀と告別式が一緒になったものを「葬式」って言うんですね。
- 妹尾:
-
そうです。「お通夜」も「葬儀・告別式」も、現在ではもともとの意味とは
違った形になっていますが、それぞれの起源を知ることで、
お葬式に対する理解がより深まりますよね。
なお、お葬式をとりおこなう葬儀社が誕生したのは江戸時代だそうです。
貨車屋、今でいうレンタカー会社が、遺体を運ぶ車を作ったことから発展したと
言われています。
でも、葬儀に葬儀社が本格的に関わるようになったのは、戦後のことだそうです。
Copyright(c) ヤシロ終活サポートセンター All Rights Reserved.