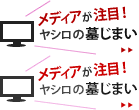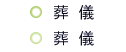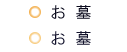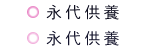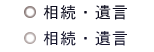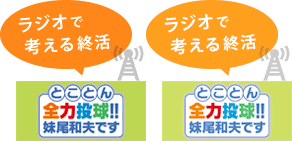終活サポート > ラジオで終活日誌
ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
第88回(2015/10/27放送)
- 妹尾:
-
今日は、霊園・墓石のヤシロの八城社長を終活アドバイザーにお迎えして、
みなさんからの疑問・質問にお答えいただきます。
社長、よろしくお願いします。
- 八城:
- お願いします。
- 妹尾:
- まずは、こちらの方から……
58歳・女性
八城社長のラジオを聞いて、エンディングノートに興味を持ちました。
そこで質問なんですが、エンディングノートに遺産や相続のことを
記入するのであれば、遺言書は必要ないのでしょうか?
そもそも、遺言書とエンディングノートの違いってなんですか?
- 妹尾:
-
エンディングノートという言葉は知っていても、具体的にどういうものなのか、
まだご存じでない方も多いようですね。遺言書とどう違うんでしょうか?
- 八城:
-
まず、エンディングノートですが、ご自身が病気をした時や介護が必要になった時、
どこで誰にどのように看護や介護をしてほしいか、とか万一、お亡くなりになられた時に、ご葬儀や埋葬に関するご希望であるとか、相続に対する考え方などを整理するために書いてみるというのがエンディングノートです。
ただ、エンディングノートには法的な拘束力がありませんので、あくまでもご自身の将来の希望や考えを書いてみることで、考え方をまとめるためのツールとしてお使いいただくためのものです。
それに対して遺言書は民法で定められた
(1)相続人の排除や遺産分割の方法など「相続に関すること」
(2)信託や寄付行為など「相続財産の処分に関すること」
(3)子供の認知など「身分に関すること」
(4)遺言の執行者の指定などの「遺言執行に関すること」
限られた項目に関して、被相続人が亡くなる前にその意思表示を一定の厳格な様式に形にしておいて、死後に実現を図るものです。
亡くなってしまうと、言葉は悪いですが「死人に口なし」ということになってしまいますので、必ず法律で定められた様式でないといけないとされています。
今は、相続問題で親族同士が争うという件数が大変増えているそうですので、そうならないためにも、遺言書を残しておくことはとても大切なことです。
ですので、遺産相続などに関してはエンディングノートで内容をまとめておいて、最終の遺言書はやはり専門家にアドバイスをしてもらったほうが良いと思います。
- 妹尾:
- 続きまして……
62歳・男性
最近、墓石のことを調べる機会がありました。
実際に見に行くと、色々なデザインがあり、また、石の色や素材も様々で、 どんなものが好ましいのか疑問に思いました。
墓石を選ぶポイントなどあれば教えてください。
- 妹尾:
- 「霊園・墓石のヤシロ」というぐらいですから、プロの社長から、わかりやすく教えてあげてください。
- 八城:
-
まず、墓石をお建てになるには、当然、墓地が無いと建てることができません。
墓地には市町村が運営をしている公営の墓地とお寺が管理している寺院墓地、そして私どものような業者が寺院と連携して管理している事業型の民営墓地の3種類があります。それぞれ特徴があり場所や格式やサービス内容によって価格が変わって きますので、よくお調べいただいて墓地の確保を行っていただきたいと思います。 公営霊園では、基本的には石材店の指定がありませんが、寺院墓地や民営墓地の場 合、石材店の指定がある所が多いので墓石だけを買って持ち込もうと思ったら、規 約で建てることが出来ない、などという場合もありますのでご注意ください。
墓石に関しては、昔は黒い石やグレーの石が大半でしたが、ずいぶんと様変わりしてきておりまして、レンガのような赤い石やピンクの石、グリーンの石や大理石のような模様のある石なども、最近では墓石に使っています。
また、形も昔は「○○家の墓」と縦書きに書いた軸石が上に乗っかっていて、その下に台石が2段とか3段とかある、いわゆる和型のお墓が多かったのですが、今は高さの低い洋風の墓石やいろんなデザインを施したデザイン墓石と言われるようなお墓もたくさんあります。
墓石に使用する石材の種類も昔からある国産の材料をはじめ中国やインド、ヨーロッパの材料など様々な国の石を使います。外国の石材に関しては当初は品質や加工が悪い製品も多かったのですが、品質管理や技術が良くなってきていますので、あまり気になさらなくても良いと思います。まずはどのような形のお墓にするか、その形にマッチする色合いの石を選び、ご予算と合わせて専門家にご相談いただいてお決めいただければ良いと思います。
Copyright(c) ヤシロ終活サポートセンター All Rights Reserved.