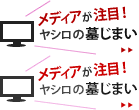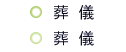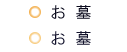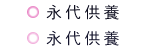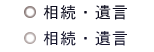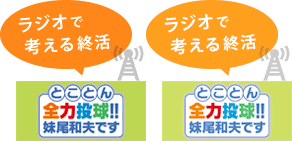終活サポート > ラジオで終活日誌
ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00~14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
第151回(2017/2/28放送)
- 妹尾:
-
今日は、霊園・墓石のヤシロの八城社長を終活アドバイザーにお迎えして、
みなさんからの疑問・質問にお答えいただきます。
- 八城:
- お願いします。
- 妹尾:
- まずは、こちらの方から……
64歳・女性
私は、死後は「樹木葬墓地」で自然に還りたいと思っています。
しかしその一方、先祖代々のお墓もあります。
私は子供たちに墓守(はかもり)や先祖供養の儀式を義務付けたくないのですが、
夫は「子供が墓を継ぐのが当たり前」と考えているようです。
先祖代々の墓との折り合いは、どのようにすればよいでしょうか?
- 妹尾:
-
夫婦でお墓についての考えが違う場合、もちろん、まずはよく話し合うことが
大事だと思いますが、お子さんの将来のこともあって難しそうですね。
- 八城:
-
ひと昔前までは当たり前であった、お墓の継承の問題が、今は、少子化や
核家族化によって、とても複雑になってきています。
この方の場合も、数年前であれば、普通にご先祖のお墓にご夫婦で入り
子供や孫がお墓参りをしてくれると思っていたのではないでしょうか?
お墓に関しては、ここ数年の間で、ずいぶんいろいろな選択肢が出てきました。
樹木葬もその一つですが、今、私どもの霊園にお越しになるお客様も
普通のお墓と仰る方は全体の1割~2割くらいで、残りの8割ほどの方は
樹木葬や永代供養といった、将来、子供や孫に負担をかけない埋葬方法を
考えておられる方がほとんどになってきました。
ただ、その考えがご家族でコンセンサスが取れていれば良いのですが
ご夫婦や親子で考え方が一致しない場合も良く在ります。
ご相談者も「子供に墓守に義務を負わせたくない」とおっしゃっていますが、
もし、子供さんが近くに住んでいるのであれば、年に数回のお墓参りをそれほど
義務と捉えなくても良いのではないかと思います。
自分のご両親のお墓参りですので、普通に考えれば、して当たり前だと思います。
ただ、生活圏が相当離れている場合や、お子様が娘さんだけで、お墓を受け継ぐ
ことが困難な場合は、将来の事も考えて、墓じまいや永代供養といった選択肢も
ご家族で良くご相談されるほうが良いでしょう。
中には、ご主人のご先祖とどうしても一緒に入りたくないと、
内緒で自分だけの樹木葬墓地を買いにくる方もあります。
ご相談者の場合、やはりご主人やお子さんとよくお話し合いをなさって、
お子様がお墓を普通に見ていける状況にあるのであれば、ご先祖のお墓に
一緒に入るのが良いのではないかと思いますね。
- 妹尾:
- 続きまして……
51歳・男性
自然に還ることのできる「樹木葬」に魅力を感じており、
先祖代々から続くお墓を樹木葬墓地に移したいと考えています。
「墓じまい」を行い、樹木葬へ「改葬」するにはどうすればいいでしょうか?
- 妹尾:
-
最近は、樹木葬を考える人が増えているんですね……
改葬するにはどんな手続きが必要で、どれぐらい費用がかかるものでしょうか?
- 八城:
-
お墓を改葬する手続きは、一般のお墓でも樹木葬墓地でも、
何ら変わることはありません。
今あるご先祖のお墓のある墓地の管理者に「納骨証明書」を新たに移す、
樹木葬墓地の管理者に「受入証明書」を出してもらい、それを、
ご先祖のお墓のある市区町村役場に持って行って「改葬証明書」を
発行していただきます。
次に、お寺さんと石材店に依頼をして、まず、お寺さんにお墓の魂抜きの
おつとめをしていただいた後に、石材店にお墓の撤去と処分をしてもらいます。
ご先祖のお墓から取り出したご遺骨を、樹木葬墓地に納骨していただければ
改葬は完了です。
費用については、墓じまいするお墓の大きさや場所によってかなり
費用が変わりますが、通常、墓じまいの工事の費用は、墓地1㎡当たり
10万円~15万円程度。
お寺さんへのお布施が3万円~5万円程度。
樹木葬墓地は、タイプによって様々ですがお一人30万円~50万円程度、
お考えいただくと良いのではないかと思います。
但し、地域や施設の内容によって、かなり金額に開きはありますので
あくまでも参考程度にしていただき、詳しくは、お近くの石材店に
お尋ねいただいた方が良いと思います。
Copyright(c) ヤシロ終活サポートセンター All Rights Reserved.